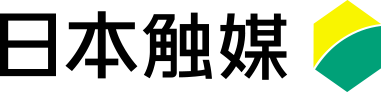光学フィルムの輝度向上 フィルムメーカーQ社 設計開発部
想定外に難航した、高輝度ディスプレイ用光拡散フィルムの開発
微粒子の専門家から提案!メラミン/ベンゾグアナミン樹脂の真球状微粒子、その効果とは

ディスプレイ用の各種フィルムを生産しているQ社。得意先から、新型モニターに使用する高輝度ディスプレイ用光拡散フィルムの開発依頼があり、設計開発部は奮闘していた。ところが、試作を繰り返すごとに、新たな課題が露呈しプロジェクトは難航が予測された。
課題
光拡散粒子としてアクリル系やシリカ粒子の配合を検討してみたが、まったく通用しない…
高輝度ディスプレイは、現行ディスプレイより少ない電力で、十分な明るさ、良質な見栄えを実現する必要がありました。それだけQ社の光拡散フィルムは重要な部材として位置付けられていたのです。
設計開発部のK氏はこのときの状況を次のように振り返ります。
「当初、我々はPETやPCなどの従来から使用していたフィルム基材上のアクリル系バインダーに対して、光拡散粒子としてアクリル系やシリカ粒子の配合を検討していました」
早速、K氏たちは、フィルム基材と粒子の設計や、粒子配合比率を変えるなど、フィルム設計変更のトライアルを何度も繰り返しました。ところが、どうやっても輝度を上げられずにいたのです。輝度の向上には、フィルム基材と光拡散粒子との屈折率差を広げ、光拡散性を高める必要があります。しかし、従来から使用している粒子による制御には限界がありました。また、輝度の向上を目的にフィルムの薄膜化も検討したのですが、Hazeが下がることによる光源隠蔽性の低下といった課題が、新たに発生します。
「その上シリカ粒子等の無機粒子で試した場合は、フィルム同士が擦れる際に傷がつきやすくなることから、使用をあきらめました」(K氏)
困り果てたK氏は、取引先や過去の事例などをあたってみましたが、解決できそうな情報を見つけ出すことができず、締め切りが刻々と迫っていました。
課題のポイント
光拡散粒子としてアクリル系やシリカ粒子の配合を検討するも、輝度をあげることができなかった
輝度向上のためにフィルムの薄膜化も検討したが、Hazeが下がり光源隠蔽性が低下
無機粒子を試すが、フィルム同士が擦れる際に傷がつきやすくなるため、使用を断念